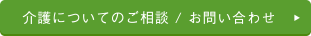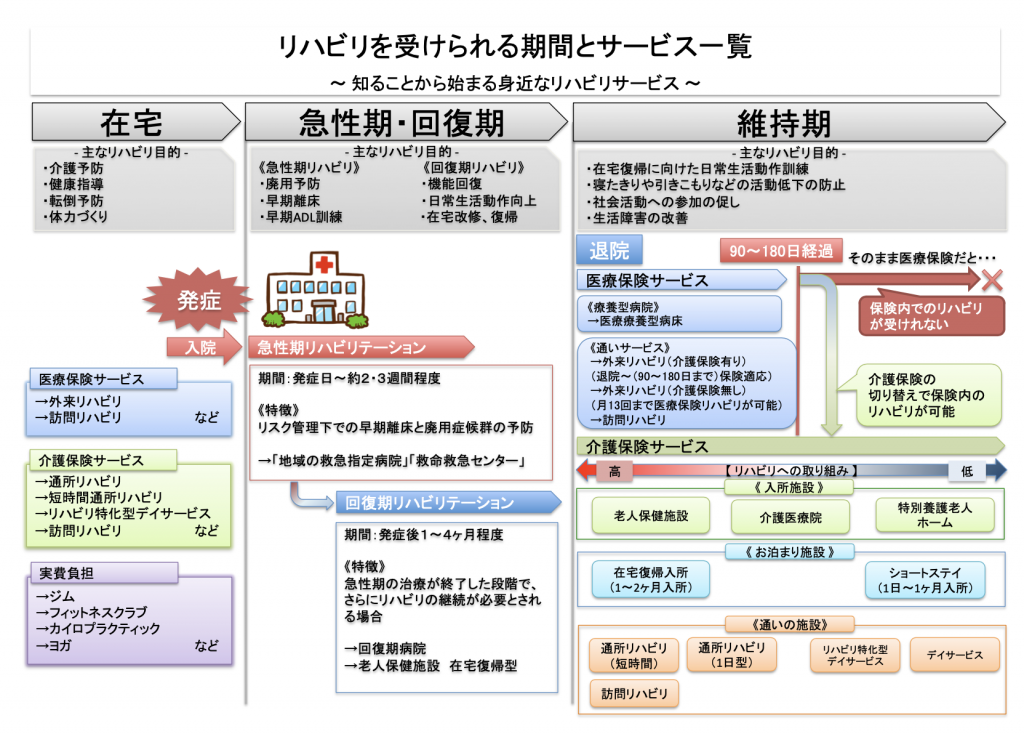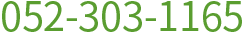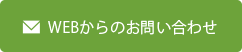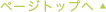-
2021.03.25
いきいき健康教室ネット「 水分の重要性 」【 医療法人親和会 富田病院 リハビリ 愛知県 名古屋市 中川区 】
富田病院リハビリテーション科 理学療法士の佐藤です。以前のいきいき健康教室ネット「なぜ加齢に伴って足がつりやすくなるのか」でも少し触れたのですが、今回は生きとし生けるものの生命維持の根幹「水分」についてお話します。水分摂取の重要性画像にあるように、人間の体重の60%以上は「体液」と呼ばれる水分です。体液は、主に下記の役割を果たします。- 細胞や組織が求める酸素や栄養素を供給
- 老廃物の排出
- 皮膚への血液循環による発汗・体温調節
- 新陳代謝…etc
上記から、人間の生命維持の根幹、源であることがわかります。脱水による弊害
生命維持の根幹である水分が減少した状態ではどのような弊害が起き得るのか例をあげてみます。・2% 喉の渇き・運動能力低下・3% 強い喉の渇き・食欲不振・4-5% 頭痛・めまい・10%以上 痙攣、死亡リスクわずか数パーセントの脱水が、体に大きな変化を及ぼすことがわかります。それでは1日にどれくらいの水分を摂取すればよいのでしょうか。そのためにはまず、1日に排出される水分量を考える必要があります。1日に排出される水分量(個人差あり)・尿1L〜1.5L前後・便0.1L前後
・呼吸0.4L前後・汗0.5L前後→合計 約2.5L水分は汗や排尿だけではなく、呼気や便などからも抜けていきます。季節や生活様式、体格、年齢、疾患などによってかなり個人差はでますが、2L前後は抜けていく可能性が高いです。それを踏まえて、どの程度水分摂取すればよいのか考えてみます。1日に摂取されるべき水分量
水分は、水やお茶、コーヒーなど飲み物を飲むことだけではなく、食事や体の中の代謝などによっても、水分が体に補給されます。これまた食事摂取量など個人差が大きいですが、食事や脂肪代謝などによって1リットル前後の水分が補給されるため、飲料水としては1L〜1.5L程度補給することが必要になってきます。皆さんは、1日に1Lから1.5Lの水分を飲まれていますでしょうか?これは結構足りていない人が多いです。軽度の脱水があるということは、「体液の役割」で申し上げたように、細胞や組織が求める酸素や栄養素を供給、老廃物の排出、皮膚への血液循環による発汗・体温調節、新陳代謝などが悪くなる可能性があります。体の疲れや、痛み、その他多くの不調が引き起こされる可能性が高まることが容易に想像できます。ただし、大量の水を飲むことや、腎不全、腎機能障害、心不全、狭心症などの疾患を抱える方などの水分摂取は要注意です。大量の水を飲むことで、体液が薄まりすぎて体のミネラルバランスを崩したり、排尿が促進され自発的脱水が起きる可能性があるため、短時間に大量の水を飲むことは控えてください。また、腎臓や心臓など内科疾患のある方は、身体の水分量が増えることで臓器に過剰な負担をかけてしまうなど、マイナスに働くこともあります。そういった疾患をお持ちの方はかかりつけの内科などで、水分摂取についてご相談ください。水分摂取が足りていないと感じられた方は、少し意識してみてください。水分といっても、コーヒーや緑茶など、カフェインを多く含む飲料ばかり飲んでいる方も、一度水分摂取について見直していただくと良いと思われます。上記のことを含め、お体の不調やお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。最後までお読みいただきありがとうございました。 -
2021.03.22
令和2年度 松和苑いきいき健康教室中止のお知らせ
-
2021.01.01
新年のご挨拶 【医療法人 親和会 富田病院 介護医療院 老人保健施設 松和苑 名古屋市 中川区】